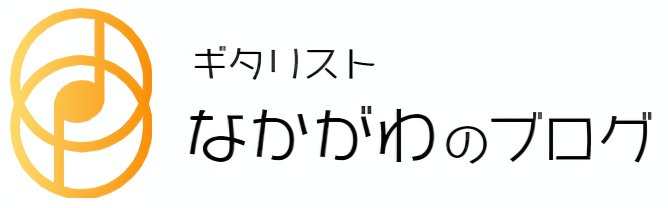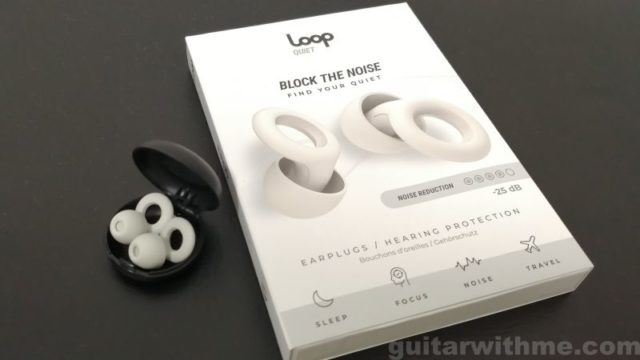「隣に住んでいる人がうるさくて…」
「家でも歌の練習が思う存分できたら…」
自宅における「音」の悩みから、やがて防音対策などと考え始めるのは、自然なことかもしれません。
しかし、多くの人は、「防音がどれほど難しいものか」を理解していません。そのため、中途半端にお金や労力を消費しては後悔するのです。
この記事では、音の仕組みや防音のポイントとともに、効果のない防音対策、現実的な防音対策などについて解説します。
防音にも2つの立場がある
防音に関する悩みといっても、大きく分けて2つの立場があります。
- 近隣に音を漏らしたくない(楽器や歌、オーディオなど)
- 近隣から聞こえる音がうるさい
以下、どちらの立場も踏まえたうえで解説します。
“音”が伝わる仕組み
防音のことを考える前に、まずは音が伝わる仕組みを理解しておきましょう。
音=空気の振動
少し強引な解釈ではありますが、シンプルにこう考えてしまうとよいでしょう。
人の声や楽器の音、テレビやステレオの音など、音が発生すると空気が振動します。この空気の振動が耳の中にある鼓膜に届き、鼓膜を振動させます。この鼓膜の振動を、人は音として認識しているわけです。
そして、この「空気の振動」が防音のカギとなります。
防音の原則
防音とは、「空気の揺れを食い止める(抑える)こと」です。
大きな音は空気を大きく揺らし、鼓膜を大きく揺さぶります。この空気の揺れをできるかぎり抑えて、鼓膜に響きにくくするのが防音というわけです。
防音を適切に施すにあたって、重要となるポイントが3つあります。
- 隙間
- 重量
- 空気の層
それぞれ詳しく見ていきましょう。
防音ポイント1:隙間を作らない
先にも述べたとおり、音は空気の振動として耳に伝わります。つまり、空気の通り道が少しでもあれば、音も通過してしまうのです。
ドアや窓は、ピタリと閉めても必ず隙間が存在します。ほんのわずかな隙間でも、空気は簡単に通過するのです。もちろん、そこから音が出入りする、という意味です。
この隙間を「完全に塞ぐ」ことが、防音における大事なポイントのひとつです。
防音ポイント2:重量で振動をブロックする
音の中でも低めの音、特にステレオの低音などは、空気を揺さぶる力が強く、壁の向こう側へと簡単に届いてしまいます。
もちろん、空気(音)が壁そのものをすり抜けるわけではありません。壁にぶつかった空気の振動が、壁の向こう側の空気をも揺らしてしまう、とイメージすると分かりやすいでしょう。
こうした現象を防ぐには、ずっしりとした重さ、かつ厚みのある壁(扉)が必要になります。分厚いコンクリートの壁や鉛のドアを想像するとよいかもしれません。
防音ポイント3:空気の層で振動を弱らせる
壁の向こう側へと伝わった音の波動が、その先でまた壁にぶつかったらどうなるでしょう?
その場合、さすがに音のパワーは弱くなり、壁の向こうのそのまた向こうへと伝わる音は小さくなります。途中に空間を挟むことができれば、音の伝達力は弱まるのです。
自分がマンション暮らしだとして、隣の部屋に住む人がうるさかったら困るでしょう。ですが、その先(隣のとなり)に住む人がうるさかったとしても、さほど聞こえてはこないと思いませんか?そんなイメージです。
音楽スタジオなどで鉛の扉がわざわざ二重に設置されているのは、こういった理由からです。
防音が難しい理由
上で述べた3つのポイントを踏まえて対処ができれば、それなりの防音効果が期待できますが、実際にはそう簡単にいかないはずです。
隙間を塞ぎきれない
前述したように、わずかな隙間でもあるならば、そこから音はたやすく出入りしてしまいます。このわずかな隙間を塞ぐのが困難極まりないのです。
たとえば窓の隙間です。開け閉めができる一般的な窓は、ピタリと閉めたつもりでも必ず隙間があいています。というより、隙間がなければスムーズに開け閉めができないのです。窓には構造上、どうしても隙間を設ける必要があります。その隙間をすべて塞ぐのは、とても難しいことなのです。
問題なのは窓だけではありません。ドアや換気扇、エアコンのダクトなど、家の中には音が出入り可能な隙間がたくさん存在します。どれかひとつの隙間を完璧に塞いだとしても、別の場所に隙間があれば、そこから音はあっさりと出入りしてしまうのです。
重くて厚い壁など用意できない
壁を伝わる音をブロックするには「重くて厚い壁」が必要ですが、もともとの壁がそうでなかった場合、どうしようもありません。大掛かりなリフォームなどができればよいですが、賃貸の一室などでは無理なケースがほとんどでしょう。
既存の壁を覆うような「ワンタッチで取り付けられる壁」を販売する業者もありますが、重さと厚みが十分でなければ大して意味がありません。コンクリートや鉛のように、「重たくて厚みのあるもの」を隙間なく付け足すことができればよいですが、あまり現実的ではないでしょう。
意味がない防音対策とは…?
個人で手軽にできる防音対策のようなものは、ほとんど意味がないと思うべきです。
参考までに、僕自身が過去に試したことのある、「ほとんど意味のない防音対策」についても触れておきましょう。
隙間テープ
まずは、ドアの隙間などに使用する「隙間テープ」の類のものです。
こうしたものは、どうにか隙間を塞ごうにも、隅のほうがうまく塞げなかったり、構造上の都合でテープを貼れない部分があったりして、いざやってみるとうまくいかないものです。
そもそも、ドアや窓の隙間を完全に塞いでしまうこと自体、換気や安全といった視点で考えると、あまりよくありません。人が暮らす居住空間としては無理があるのです。
隙間テープとは、リフォーム的な「まともな防音対策」を施したのち、その仕上げのような形で使うものだと考えたほうがよいでしょう。
遮音シート
続いて、「遮音シート」のようなものです。
遮音シートは、それなりに重量があるため、気軽に貼り付けたりできるものではありません。壁などに貼り付けようにも、上のほうがすぐに取れてしまいがちなのです。よほど強力なもので打ち付けるなどしなければ、あっさりと剥がれ落ちるでしょう。
仮にうまく貼り付けられたとしても、自分で持ち上げられる程度の重さ、手で摘めるような厚みのシートで、大きな音の波動などブロックできるはずがありません。加えて、「隙間が空いてはいけない」という問題も、素人ではなかなかクリアできないでしょう。
遮音シートというものは、防音仕様の重く厚い壁などをつくる際、その内部に組み込むものであって、これ単体でどうこうというものではない、と思うべきです。
効果の見込める防音対策とは…?
防音は難しいから諦めるしかない、というわけではありません。費用さえかけられるなら、効果的な対策も可能ではあるのです。
業者に依頼して工事をする
業者に防音工事を依頼できるなら、それなりの効果が期待できます。
もちろん、しっかりとした防音を施すには、それなりの費用が必要となります。音楽専門誌『サウンドデザイナー』の記事(2008年5月号)によれば、6畳の部屋を「最低限の防音仕様」にするとして、およそ250~300万円ほどかかるそうです。プロスタジオ並の防音仕様にするならば、それを遥かに上回る費用が必要なのは言うまでもありません。
ちなみに、防音工事には大きく分けて2種類のタイプがあります。ひとつは設計図に基づいて大工が行う工事、もうひとつはあらかじめ作られた防音パネルを持ち込んで組み立てるタイプの工事です。
大工が行う工事の場合、自由度が高い反面、担当者の腕によって防音の効果に差が出るため、難しい一面もあります。一方、防音パネルを持ち込む工事の場合、安定した防音効果が期待できるものの、費用がやや高めで、細かいオーダーができないことが多いようです。
屋内用の防音室を導入する
ヤマハの「アビテックス」のような、室内設置型の防音室を導入する方法もあります。
こうした室内設置型の防音室は、楽器や歌を自宅で存分に楽しみたい人には、よい選択のひとつかもしれません。ただ、こうした防音室は、あくまでも「音漏れを軽減するもの」であり、これで無音になるなどと勘違いしてはいけません。大雑把な感覚ですが、「3~4割ほど音量が抑えられる」とイメージするのがよいと思います。
防音室の価格は、広さや防音性能、設備オプションなどで変わります。アビテックスの場合、4畳ほどの広さで100~200万円程度、電話ボックスのような狭いもので50~100万円程度です。
簡易組み立て式の電話ボックスタイプで、30~40万円程度の比較的安価なものを販売するメーカーもありますが、隙間や重さといった視点から考えても、防音性能は落ちると思ったほうがよいでしょう。
引っ越しをする
賃貸マンションやアパートでの騒音に悩む人にとっては、引っ越しこそが最も費用対効果の高い方法かもしれません。
引っ越しには多くのお金と労力が必要ですが、ほとんど効果のない中途半端な防音対策にお金を使ってしまうより、思いきって引っ越しをしたほうがマシなケースは多々あるでしょう。
ただ、引っ越した先にも同じような騒音主が住んでいる可能性があります。物件は慎重に選ばなければなりません。
番外編:耳栓を使う
騒音に悩む人にとっては最も手軽で、それなりに効果のある対処法です。
かつて、僕自身が騒音に悩んでいた頃、藁にもすがる思いで耳栓を購入したことがあります。いざ使ってみると、思いのほか効果がありました。
効果の度合いを言葉で伝えるなら、両耳を指でグッと塞いだ状態から1割程度、ほんの少しだけ力を抜いた状態、といった感じでしょうか。
いちいち耳栓をしなければならないのも嫌な話ですが、騒音による精神的苦痛を多少は軽減できると思います。
おわりに
音の仕組みや防音のポイント、さまざまな防音対策について解説しました。
ここまで読んだ人ならば、防音というものがどれほど難しいことか、よく理解できたことでしょう。世の中には手軽な防音グッズなるものがいくつも存在しますが、それらにどの程度の効果があるのか、この記事をヒントにすれば、おおよその判断がつくはずです。
「100万円クラスの防音室を設置しても、軽減できる音は3~4割ほど」
この事実を常に頭に入れておきましょう。大事なお金を無駄に失わないよう、気をつけてください。