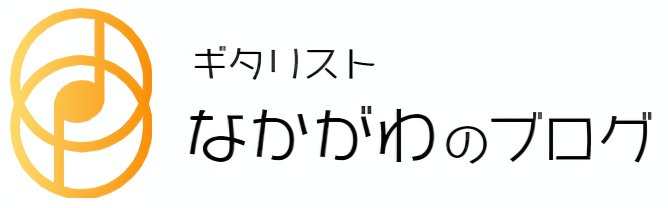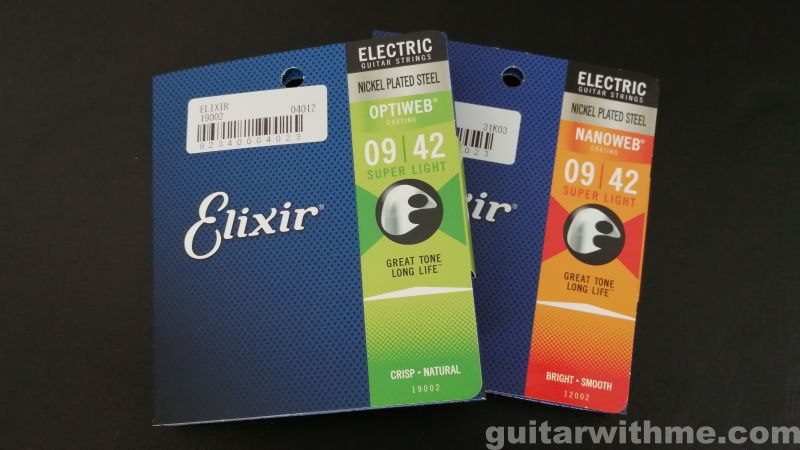何を隠そう、僕自身も「音楽の専門学校」とやらに通っていた過去があります。そのため、音楽の専門学校に行こうとする人の気持ちは分かるつもりです。専門学校に行けば…
- 歌や楽器がうまくなる
- 音楽理論などの知識が身につく
- 同じ夢をもつ仲間との繋がりができる
- 音楽業界とのパイプができるかも…
などと期待をするのでしょう。しかし、そう思った人はいわゆる「カモ」です。上にあげたものは、わざわざ音楽の専門学校に行って高い学費を払わなくても手に入るのです。
この記事では、音楽の専門学校の是非について、僕自身の体験をもとに解説します。
その学びに学費分の価値は本当にあるか?

「音楽の専門学校に行ったものの、何の意味もなかった」などと言うつもりはありません。勉強になったこともあったのは事実です。ただ、その学びに「学費分の価値はあったのか」と考えると、とてもそうは思えないのです。
音楽の専門学校といってもいろいろありますが、2年間の学費は100万円以上200万円以内の場合が多く、150万円前後がひとつの目安かもしれません。仮に学費が150万円だとすると、「それに見合ったリターンが本当にあるのか」を考えるのが重要なわけです。
たとえば、1500円でギターの教則本を1冊買ったとします。1冊の教則本でもたくさんの学びがあるのは、読んだことがある人なら分かるでしょう。その教則本を10冊買ったら1万5千円、100冊買ったら15万円です。そして1000冊、部屋を埋め尽くすほどの教則本を買って、ようやく150万円になるわけです。専門学校での学びに、部屋を埋め尽くす「教則本1000冊」と同等の価値があるのか、と考えてみるとよいかもしれません。
「おれは専門学校に行ったけど意味があったぞ!」「私は行ってよかった!」と主張する人もいます。その人らが、そこで何かを得たのはきっと事実でしょう。ですが、その主張には「払った金額に見合った対価があったかどうか」という肝心な視点が欠落しているような気がするのです。払った金額と、そこで得たものが釣り合っていないなら、それは「損をした」ということです。
「音楽の専門学校出身で成功した人もいる」という意見もあるでしょう。たしかに、成功した人にとっては、高い学費を払った意味があったのかもしれません。ですが、この手の話では、きちんと「分母」を考えるべきなのです。
たとえば、どこか1つの学校に注目してみましょう。「毎年の入学者数の平均×学校の運営年数」で、これまでの卒業者数がおおよそ割り出せます。そのなかで、成功したといえる人が何人いるでしょう?割合でいえば、きっと1%未満でしょう。1%未満の成功者より、99%以上の「その他」に注目したほうが現実的なのです。「卒業生の99%以上が成功していない学校」に、一体どれほどの価値があるというのでしょう。
そもそも、その1%未満の成功者も、「音楽の専門学校に行ったおかげで成功した」とは言いきれないはずです。専門学校どうこうは関係なく、ずば抜けた才能があったから成功したのかもしれません。人よりも積極的に行動を続けた結果、成功を手にしたのかもしれません。たまたま運よく成功したのかもしれません。自分で一生懸命、練習や勉強をしたから成功したのかもしれません。要するに、成功の要因が「専門学校に行ったおかげ」ではないかもしれないのです。
音楽の専門学校に限った話ではありませんが、人は「勉強する、学ぶ」といった話になると、金銭感覚が麻痺しがちです。お金持ちの人は別として、多くの人は100万円を超える買い物を簡単にはしないでしょう。しかし、「学び」という領域になると、割とあっさり大金を払う人が出てきてしまうのです。
そして、そこにつけこむビジネスが世の中にはたくさん存在します。もちろん、音楽の専門学校もそのひとつです。
音楽理論は「本」で学ぶほうがいい

かつての僕が学校で習った音楽理論は、一般的に売られている理論の本よりも随分と踏み込んだ内容で、小難しいものでした。音楽理論の本を出版する場合、あまりに難しい内容だと売れないので、「7日でわかる音楽理論」といったものが書店には並ぶのでしょう。
とはいえ、一部の本はかなり踏み込んだ内容まで扱っているのもまた事実です。たとえば、清水響さんが書いた『コード理論大全』という本には、僕が音楽学校で習った小難しい話のほぼすべてが収録されていました。(というか、たぶんそれ以上の内容)
つまり、音楽の専門学校で習う音楽理論は、この3,000円の本のなかに集約されているのです。となると、わざわざ高い学費を払って、専門学校で理論を学ぶ理由はないわけです。
もっとも、音楽理論とはそれなりに難解なものです。上で紹介した本も、中身はかなり難しい内容なので、読んでもまともに理解できない人が多いでしょう。その難しい話を学校でわかりやすく解説してくれるなら、学校で学ぶ意味もあるかもしれません。ですが、実態としては「そうでもない」のです。
音楽理論の授業において、「猿でもわかるレベル」にいちいち噛みくだいていると、2年間のうちにやらなければいけないカリキュラムが終わらないのです。理論の授業は生徒20人など大人数でやるのが普通で、どんどん進みます。理解できない人は単純に置いていかれます。
そのため、わかりやすさという点では、「7日でわかる音楽理論」「猿でもわかる音楽理論」といった類の本を買って読んだほうがマシなのです。いまの時代なら、YouTubeなどでわかりやすく解説している動画もあるでしょう。それらを利用して下地を作ってからであれば、少し難しい理論書の内容も理解できるはずです。
何冊か理論書を買っても、せいぜい1万円程度でしょう。わざわざ音楽の専門学校に高いお金を払って、そこで理論を学ぶ理由はないのです。
実技の授業は意外と中身がない

もちろん、音楽の専門学校では実技の授業があります。そこで特別な教えを受けるために高い学費を払うのだ、と考える人も多いでしょう。ですが、その教えも100万円以上払う価値があるものなのか、やはり考えるべきです。
基本的に、実技の授業に出席するだけでは技術は向上しません。当然ですが、自分で長い時間をかけて鍛錬しなければレベルアップはしないのです。では、実技の授業に出席するメリットは何でしょう?それは、「自分では気づけない点を指摘してもらえること」です。そんな指摘が授業の中にたっぷりと詰まっていればよいのですが、実際には「そうでもない」のです。
具体的にどんな授業内容だったのか、あくまで僕の場合ですが、簡単に説明しましょう。基本的な授業の形式は、1回の実技レッスン(ちなみにギター)が45分ほどで、生徒3人に対して先生が1人、というものでした。
授業の冒頭では、宿題だったスケール練習のようなものを全員で弾き、だんだんテンポを上げていきます。(これだけで10~15分ほど使っていたような…)
そのあとは、あるコード進行に沿ってアドリブ演奏をする、といった内容。先生がお手本を示したあと、3人の生徒が1人ずつ演奏します。1人の演奏が終わると先生がアドバイスをして、次の生徒に…という流れ。1人が何分間か演奏するので、それなりに時間がかかります。
それをもう1周したり、あるいは来週の予習のようなことをやったりして、45分などあっという間に終わります。
つまり、45分という時間のなかで、先生からのアドバイスを受ける時間など、実質的にはほとんどないのです。やっていることの大半は、「家で1人でできるんじゃ…?」といったもの。先生のお手本は家では見られませんが、うまい人の演奏など、いまやYouTubeなどでいくらでも視聴できる時代です。そう考えると、この授業にどれほどの価値があるのでしょう…?
いちばん微妙なのが、ほかの生徒の演奏です。あまり上手ではないほかの生徒の演奏など、聞いていても時間の無駄なのです。先生がほかの生徒へ何かアドバイスしても、その内容は自分にとって役に立たないものだったり…。
といった具合に、45分という時間の中身は、意外にもスカスカだったりするのです。
音楽の専門学校といってもいろいろあるので一概には言えませんが、実技の授業もカリキュラムのようなものがあり、それに沿って淡々と進んでいく場合がほとんどだと思います。無駄の多い、中身の薄い実技レッスンが1年、2年と続いて、学費は150万前後。実際に音楽の専門学校に通った僕としては、「とても割に合わない」と思いました。
ちなみに、先生からのアドバイスというのは、技術的な濃いアドバイスとかではなく、あっさりとした感想のようなものばかりでした。実技レッスンというより、アドリブで演奏を披露して、ただ感想をもらうだけです。
「どうしてもこの先生に演奏を聞いてほしい」「どうしてもこの先生からアドバイスを受けたい」というのであれば、別によいのかもしれません。ですが、特に崇拝もしていない学校の先生から、「なんとなくの感想」をもらうために高い学費を払うのは、あまりに馬鹿げているのではないでしょうか。
複数人形式のレッスンは罠
音楽の専門学校で、実技系の授業が複数人形式になる、というのはよくあるパターンだと思います。
「1対1、マンツーマン形式のほうがいいんじゃない?」と思った人は正解です。上でも述べたように、複数人形式だと、たいして上手ではないほかの生徒の演奏(または歌)を何分も聞かされる、という無駄が発生してしまうのです。
学校側は、「複数人形式の授業だと刺激がある」「1人では得られないものが…」などと言ったりしますが、それは大嘘です。学校側がなぜこんな嘘をつくかというと、「本音」を隠したいからです。
1対1の商売というのは、時間ばかりが取られ、「稼ぐ」という意味では非効率です。客単価をグッと上げれば儲かりますが、あまりに高いと客が来なくなります。美容師などの職が儲かりにくいのも、この理屈でしょう。それに対し、1人で同時に100万人の相手すらできるユーチューバーなどは、短時間で効率よく稼ぐことができたりもするわけです。
音楽の専門学校に話を戻しましょう。1対1の実技レッスンをしても、1日で相手にできる生徒の数は、そう多くありません。個人事業主ならともかく、法人としてはさほど儲からないのです。
だからといって、1人の講師に12時間以上など、無理に授業を詰め込むわけにもいきません。より多くの生徒を相手にしようと新たに講師を雇えば、新たな人件費が発生してしまいます。授業料を上げすぎると客(生徒)がつきません。
こうした問題を比較的簡単に解消する方法が、「複数人形式」の導入なのです。講師1人につき、生徒を2人にすれば儲けは2倍、3人にすれば3倍です。同じ時間でも、相手にできる生徒の数は倍増し、儲けも倍増するので、学校側としては「非常においしい手段」なのです。
こうした事情があり、学校側は複数人形式のレッスンをやりたがるのです。しかし、「効率よくお金を稼ぎたいので、複数人形式にします」とは絶対に言いません。その本音をもらすと、「酷い学校」と思われてしまうでしょう。だから、本音は隠したいのです。そのための最高の言い訳が、「複数人でレッスンすると刺激がある」という言い回しなのです。
そもそも、刺激など別の手段でも簡単に得られるはずです。好きなアーティストのライブを見に行って、大きな刺激を得ることもあるでしょう。自身がライブハウスのステージに立ち、一緒に出演したほかのバンドから刺激を得ることもあるでしょう。もっと手軽な手段としては、YouTubeなどで誰かの演奏動画を見て、そこから刺激を得ることもあるでしょう。
学校側の詭弁に騙されて、本質を見失ってはいけません。
繋がりなんてSNSを利用すればいい

音楽の専門学校に行けば、「仲間との繋がりができる」という人もいます。ですが、それこそ今の時代なら、ネットを利用すればよいのです。
ツイッターやインスタグラム、YouTubeなどを活用すれば、同じ趣味をもった仲間などいくらでも見つかるでしょう。たまたま同じ学校で出会う人より、ネットをうまく利用して、自分と合いそうな人とだけ交流するほうが合理的とも言えるのです。
ただ、控えめな性格の人の場合、ネットで誰かと交流するのは難しいかもしれません。しかし、その人が専門学校に行くことで、たくさんの仲間に恵まれるかというと、それはそれで難しいはずです。専門学校に行けば仲間ができる、という保証はないのです。結局のところ、本人の積極性次第でしょう。
仲間とは別に、音楽業界との繋がりに期待して専門学校に行こうとする人もいるかもしれません。たしかに、優秀な生徒が仕事を紹介されるとか、新たにデビューするバンドのメンバーに抜擢されるといったことが、僕の知る範囲でもあったのは事実です。
ただそれは、よほど優秀な人や、よほど魅力的な人(外見を含む)の場合で、そんな人は生徒全体の1%もいません。その1%に入れるくらい優秀、または魅力的なら、音楽学校のパイプなどに頼らなくても、自分で繋がりが作れるはずなのです。
ツイッターやYouTubeなどを利用し、自分の魅力なりをうまくアピールできれば、それが仕事に繋がる時代です。高いお金を払って音楽の専門学校を経由する理由は、いまの時代、もうないはずです。
おわりに

誰かにお金を払い、何かを教わること自体は何の問題もありません。僕自身も、これまでにたくさんの本を買い、そこから多くのことを学びました。(書籍を購入することも、お金を払って他人から教わる行為といえるでしょう)
問題は、音楽の専門学校の授業内容に無駄が多く、払う学費が高すぎることです。高い学費を納めさせるわりに、そこで得られるものは、別の手段でもっと安く、あるいは無料で得られるものばかりなのです。
残念ながら、音楽の専門学校とは、「夢をもつ若者」あるいは「夢をもった我が子を応援したいと思う親」の味方ではありません。そんな人らから、100万円以上の大金を巻き上げる「ビジネス」なのです。
100万円~200万円など痛くもかゆくもない、というお金持ちの人が通うのなら、さほど問題はないかもしれません。ただし、お金持ちとはいえない人の場合、別の手段を検討したほうがよいと思います。
学びも経験も繋がりも、もっともっと安く手に入る時代ですから。